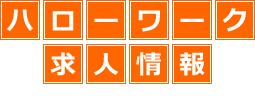回答
休業を取得した従業員がいるということで、職場の中に取得しやすい雰囲気があるというように解釈できます。
解説
まず産休と育休は法律が違うということを憶えておいてください。
産休は、産前産後休業と言われるもので、労働基準法に取得を定められております。
育休は、育児・介休業法で定められております。よく育休の取得実績は向上と言われておりますように本人の申し出による休暇です。
一方、産休に関しては、規制法の労働基準法規定のため、必ず全ての出産する予定の女性従業員を産休期間、就業させてはならない(禁止規定は産後のみ)という強行規定です。
ここを同じに考えないようにしましょう。
さて産休です。労働基準法に出産前の6週間、出産予定の女性従業員が休業を請求した場合は就業させてはならない。
そして実際の出産日が予定日後だった場合はその日数分延長されます。
ただし、当該の女性が請求しなければ就業させても差し支えない。
出産後においては、8週間を経過しない当該の女性従業員を、使用者は就業させてはならないと定められております。
それが産休というものです。また、育休とは 、育児・介護休業法で、労働者(男女問わず)の申し出により、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることが出来るというものです。
この法律は平成21年に改正され22年に改正法が施行されました。
改正法により、取得できる対象労働者が、1年以上同じ会社に勤務し子が1歳になる日を超えても引き続き雇用される期間雇用者にも適用の幅が広げられました。
ただし 、日々雇用される者幅対象にはなりません。
また、保育所に入所を希望しているが、入所出来ない場合や、子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降、子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育する事が困難になった場合、 (これはつまり、育児休業取得者の配偶者が1歳を超えて以降は養育するため、本来は育休休業期間が1年で終了する予定であったが、その配偶者が、病気になってしまった場合)、子の年齢が1歳6ケ月に達するまでの間、育児休業が出来るようになりました。
ご質問の意味は、これらの休業を取得した従業員がいるということで、職場の中に取得しやすい雰囲気があるというように解釈できます。